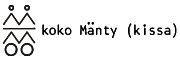頭の中には、いつも(決して意識的でもないし、明瞭さにも欠けるのだけど、流動的で有機的な)美しい景色(それは、あるいは光だったり影だったり、光と影の間の青だったり)が浮かび上がる、というよりは在ります(居ます、に近い)。そして、それがいつも写真で撮りたいもの、正確にはイメージ化したいものだと思っています。いつも在るのです、この頭の中に。どんな喜びやいざこざや美しさの中にあっても。それが僕の原動力です。生きる喜びです。だから、いつも輝いています。この世界が内側にあるのか、外側なのかわからなくなるのです。
・
大分の祖母宅の玄関には、ガラガラと戸を開けて、同じ集落で同じ名字、同じ年の同じ月の同じ日に生まれた(つまり同級生の)女の子が立っていた。彼女は年相応な肌感を保ち、農協のコスチューム(それは彼女が祖母に農協の季刊誌を配達に来たことで知ることになった)を身に纏い、はにかみながらこう言った。「まっくん、帰っちょったん?お嫁さん?」妻に愛想よく会釈しながら、乾燥する冬場に同い年であることを感じさせる僅かなホウレイセンの皺をぐっと上げて笑顔を向けた。きっといつも同じ星座占いを見ていた彼女とは、いつの間にか、彼女の性格と、僕の性格のズレみたいなものから、自ずと会話は減っていった。幼稚園から高校までずっと一緒ではあったが、あの地域ではそれほど珍しいことでもなく、思春期特有の男女の隔たりも助け、疎遠になって行った。少し暗い子、とすら思うようになっていた節もあり、その嫌味のない社交的な笑顔は自分たちが年を重ねたことを皺以上に感じさせた。彼女にも“いろいろ”あったのだ。そのまま玄関越しにテレビの部屋でコタツに入ったままの祖母と顔を合わせることもなく、高齢者との会話の独特のボリュームの明るい発声を聞いた時には、彼女への印象は一層子供時代から離れていった。
・
九州と言ってもリアス式の谷間で前面に海を抱えているその場所は、北からの風が容赦なく吹き込んできて、東京の寒さよりも、人の気配の少なさも手伝って、かなり厳しい。彼女の唇は少しただれ田舎の息ぐるしさすら感じさせるが、ただ、玄関のモザイクガラス越しに彼女を後ろから、大分県で唯一海に陽が落ちるその地の特性もあって、とても強烈な、しかしどこまでも柔らかい黄金色が包んでいた。彼女の笑顔に比例するように煌々と燃える黄金色。どこかの商店から寄贈されたのか、知人か親族に譲り受けたのか、周りの銀がすすけ落ちて、青や黒や赤茶の斑点を持つ、上のところに「贈」と消えかけた金色の文字で書かれた鏡が裸のまま玄関に掛けられていて、そこに映る彼女の反対側の顔はとても美しく青かった。それは光りすぎていない蛍光灯の緑色のような、ホテルの部屋の白い壁に回り込むようにぼやっと満たしている陰の青のような、黄金色との間でくっきりと彼女の右半身ごとくるんでいた。静かな、時を止める、古びた銀色の青。
・
そんな話が、あったのかなかったのか、そのような青が僕の頭の中に在るのです。
2018年8月8日 koko Mänty (kissa) ~ 森へ ~ 成重松樹 Matsuki Narishige