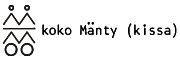その道はほとんど忘れ去られてしまっているかのようでした。ぼんやりと当時の面影のまま何のお役所的手入れもなく、まるで亡霊のようにそこにあるだけで、それは僕に、郊外のデパートメントの屋上に出鱈目にはめ込まれた観覧車が雨に打たれている姿を思い出させるのでした。そのころの九州北部は特段雨の多い時期で、その道中に人っ子一人居合わせなかった(ある道しるべのような者には出会ったのだが。。)ことがただそうさせたのかもしれません。そこは僕が幼稚園から小学校まで通った、つまり通学路です。
その道はほとんど忘れ去られてしまっているかのようでした。ぼんやりと当時の面影のまま何のお役所的手入れもなく、まるで亡霊のようにそこにあるだけで、それは僕に、郊外のデパートメントの屋上に出鱈目にはめ込まれた観覧車が雨に打たれている姿を思い出させるのでした。そのころの九州北部は特段雨の多い時期で、その道中に人っ子一人居合わせなかった(ある道しるべのような者には出会ったのだが。。)ことがただそうさせたのかもしれません。そこは僕が幼稚園から小学校まで通った、つまり通学路です。
あの頃、その地域の大人たちは、誰もが保護者のように僕たちを見守っていてくれたように思います。通学路は、小さな山を越えていきます。そこには子供たちに“頂上”と呼ばれる確かな頂があり、当時僕らにとっては険しく、途方もないようなストーリーが随所随所で生まれそうな気配を感じれるほどの立派な“山”だったのです。実際に数多くの思い出がそこにはあります。野苺を摘んだり、アケビの所有権を言い張ったり、蜂と闘ったり、山犬に出会ってしまって泣きそうになったり、喧嘩したり、グリコをしたり、クワガタを捕ったり。そういったものの全てはあの山にあったのです。





 (この先、“杉の木トンネル”と子供たちに呼ばれるその入り口)
(この先、“杉の木トンネル”と子供たちに呼ばれるその入り口)

 (杉の木トンネルでまず始めに出迎えてくれる池。“ウランタン池”。当時は単に大人がそう言っていたのをカタカナで記号的に覚えていたが、再度出会って、ふっと気付いた。“裏の田の池”だったのだ。。)
(杉の木トンネルでまず始めに出迎えてくれる池。“ウランタン池”。当時は単に大人がそう言っていたのをカタカナで記号的に覚えていたが、再度出会って、ふっと気付いた。“裏の田の池”だったのだ。。)
あの頃から20年ほど経って、再び登ったその“山”は、まるで丘のようにささやかなものでした。胸の真ん中辺りに風穴が空いたかのような冷涼とした淋しさを感じずにはいられませんでした。
時を重ねるごとにあらゆるものは変わっていきます。人は環境そのものも変えて生きていきます。生活環境、労働環境、自然環境。しかし、この“通学路”はほとんど変わっていませんでした。“変わらぬもの”に出会い、自分がどれほど変わったのかを目の当たりにしたのです。それはまさしくタイムスリップした心地でした。
ただ、おかしなものですね。樹々は年ごとにその年輪を重ね、草花は日々景色を細かく変え続け、全くとして同じ景色など出会うことも叶わないのに、僕は“変わらない”などと自身の勝手を嘆いてしまっているのですから。そして、驚くことに僕らの細胞も日々生まれ変わり約6年周期で殆ど入れ替わってしまうとも聞きます(神経細胞系は別としても)。不思議なものです。どうやら肝心なものは“全体の中”にあるのかもしれませんね。僕らを決めるものは、目に見えるモノや、景色などではないようです。
細胞と細胞には境界なんて決められないのかもしれません。空と地上に境界がないように。僕たちは“想い”で生きているのでしょうか。愛する人とつないだその手は“境目”を無くし、二人は一つに、一つのことは二人によってもたらされるのかもしれません。それがおそらく人生と呼ばれるものになるのではないでしょうか。そうであればいいなあ、と。