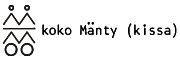グッタペルカ。
彼は、今青信号になったばかりの交差点を1986年製のパナソニックの赤と白が配色されたロードバイクに股がって渡ろうとしていた。心の中で、“口をつく”というようなタイミングで、すでにその言葉をつぶやいていた。
幅6メートルほどある、わりとゆったりとした青信号になったばかりのその横断歩道で、女性がうつぶせるように転んでいた。辺りは一瞬どよめいたがすぐに日常を取り戻していた。ただ一つ、そこに特別製を見出すとすれば、辺り一面に広がった白いヨーグルトであろう(おそらく近くのコンビニでランチのデザートとして買ったのだろう。あるいは特別な民間療法にでもはまっているのかもしれない。)。しかし、それすらもほとんど日常を奪うのには効力が無かったようだ。
彼は雨に濡れた湿布のことを思い出していた。
騒ぎにならずに済んだのは隣に連れの女性がいたからであろう。二人とも銀行員ののような制服を着ている。連れの女性は、いかにもランチに出かけるために作られたとでもいうような赤い長財布を片手に、淹れたての紅茶にたっぷりのミルクを注いだような色のカーディガンを肩に軽くかけるように羽織っていた。誰かがそっと気遣かってかけたかのような完璧な羽織り方だった。あまりに完璧だったので信号が点滅を始めて注意を促すアナウンスが耳に入るまで、彼は渡ることを忘れてしまうほどだった。
そして、白いヨーグルトの上で、同じように急いで渡ろうとした薄緑色の作業用ブルゾンとグレーのスラックスを合わせて着こなしていた中年の男性が、アイスダンスを踊るように転んだ。
グッタペルカ。
彼は去り際に、もう一度、今度は口に出してつぶやいていた。
彼はそのまま人気の乏しい下り坂を勢い良く下りながら、2週間前にこの坂で、同じように下りながら考えていたことを思い出していた。
—何処か懐かしい香りが鼻を強くくすぐった。ああ、と、記憶の糸を辿る、もどかしさと心地よさを感じさせられるタイプの香りだ。彼の頭の中はすでにある光景で満たされていた。その光景はおそらくハイスクール時代の入学事務室に繋がる渡り廊下だったと思う。それはそこにあった。
《その香りはキンモクセイだった。不思議なものだ。触ることも目に観ることもできないその記憶こそが、確かにキンモクセイと同じ役割を担っている。一年のわずかばかり漂うその香りはたちまちに“僕にとっての一連の”キンモクセイを表象させてしまったのだ。しかし、皮肉にもそれは一年のほとんどを忘れて過ごしているということでもある。我々の多くはそれについて、いつだって、幸か不幸か、自由か不自由か、と議論したがるものだが、はたしてそれは意味をなすのだろうか。花をつけたキンモクセイも、忘れ去られたキンモクセイも、キンモクセイがキンモクセイをやめたことは無い。別にキンモクセイが秋を運んでくるわけでもない。ただ我々がそれを感じるかどうかだ。一年の殆どをそこにキンモクセイがあることを、 僕は忘れている。それでもキンモクセイはただただしかるべき時に、しかるべき芳香を漂わせる。今も何処かの大海原でクジラが空を舞うように。
僕はどのように生きれば良いのだろう。》
彼は、最早二週間前の香りを完全に失った下り坂を何処までも下りながら、もう一度慎重に絶妙なタイミングでこうつぶやいた。
グッタペルカ。
《NEWS/お知らせ》のページにて「11月の臨時休業のお知らせ」もアップさせていただきましたので合わせてご確認いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
koko Mänty (kissa) 成重 松樹